 |
■国史跡・永代人馬施行所■
江戸呉服町の豪商かせや与兵衛が中山道の
旅の難儀を助けようと金千両を幕府に寄付した。
その利子で文政11年(1828)に設置された
施行所の一つである。
11月から3月まで峠を越える旅人に粥と焚火を、
牛馬には年中桶一杯の煮麦を施行した。
その後、土砂崩れにより流失したが、嘉永5年
(1852)現在地に再建され明治3年(1870)まで
つづけられた。

|
|
|
 |
■三十三体観音像■
中山道の退廃とともに毀損し、荒廃されるままに
放置されていた石仏を昭和48年調査発掘により
旧中山道沿いに安置した。
千手観音13体、如意輪観音4体、馬頭観音10体
不明2体で、4体は未発見である。

|
|
|
|
|
 |
■国史跡・唐沢一里塚■
慶長9年(1604)徳川幕府は、永井白元・本多重光
の両名を中山道の一里塚奉行として、江戸日本橋より
一里(4km)ごとに道の両側に五間(9m)四方の塚を
築き、その上に榎木か欅を植えて旅の便をはかった。
村内には、上組・鍛冶足(江戸より五十里塚)・唐沢・
東餅屋の4カ所あった。
唐沢の一里塚は、現在でも街道の両側に残り、
道中でも保存の良い所として有名である。

|
|
|


|
■国史跡・歴史の道資料館■
かわち屋
文久元年(1861)3月10日の大火で焼失したが、
その年の11月本陣・脇本陣などと同じく再建された建物
である。
和田宿の旅籠では規模が大きく、出桁(でげた)造りで
格子戸のついた宿場建物の代表的な遺構である。
江戸末期の建築様式をよく伝えている。

|
旅籠の構造 絵・中西立太
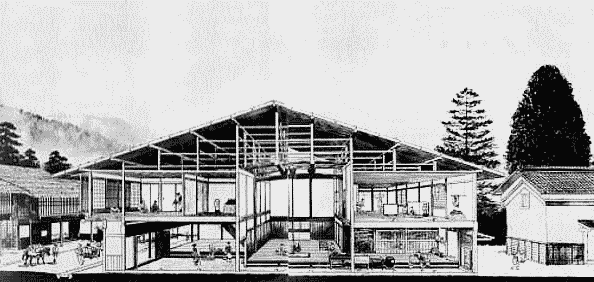

|
|
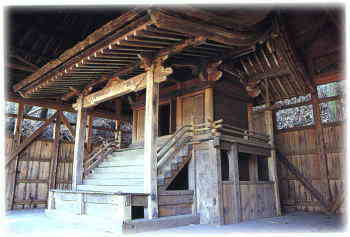 |
■新海神社本殿■(上町・中町)
和田郷が大井氏の所領であった関係から、和田郷では
新海神社を祭った。この神社は、八幡社・熊野神社と共に
和田宿守護の三神として特に祭祀された神社である。
このあたりでも数少ない、三間社流造りの本殿で全体を
朱・群青・白で彩色した貴重な建築である。

|
|
|


■遊湯パーク和田宿温泉ふれあいの湯■
泉温は40度、泉質は、カルシュウム・ナトリウム硫酸塩等で、神経痛・筋肉痛・
五十肩・冷え性・慢性消化器病・疲労回復に効果があります。
●利用時間:4月〜9月 午前10時〜午後10時まで
10月〜3月 午前10時〜午後9時30分まで
●利用料金:大人(高校生以上)300円・回数券(11枚)3000円
小人(小中学生)200円・回数券(11枚)2000円
●お問い合わせ:0268−88−0001
■月曜日は、お休みのためご利用出来ません■
 |
|

 |
■男女倉(おめぐら)遺跡■
本州でも和田峠の黒耀石は、質が良く広範囲に豊富に
産出された。この黒耀石で作られた石器が遠く東北・
関東・近畿地方まで搬出されていたことが、それらの
地方の発掘により明らかになっている。昭和27年頃より
旧石器時代の遺跡として注目され数回の発掘調査が
行われた。昭和49年と50年、新和田トンネルの開設に
ともない大規模な発掘調査が行われ、数万点に及ぶ
黒耀石器が出土している。
■黒耀石の湧水■(男女倉)
太古から涸れることなく湧きだしている「黒耀石の湧水」
長い年月をかけて黒耀石の層を通り抜けてきた水は、
硬度が1以下という大変軟らかい特徴のある湧水に
変化しています。
遠くは、近畿地方からもこの水を求めて来ています。
このあたり一帯は、男女倉遺跡埋蔵の保存地です。

|
|
|